研修はFrameVRのシンプルなアバターが臨場感を演出するのにベストだった件
ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

オンライン会議のデメリットはFrameVRのシンプルなアバターで解消
すでに、オンライン会議も普及して、ネット回線やアプリ設定は慣れてきたことでしょう。
そこで、私(木村)は、もう一段階オンラインの活用を検討してもよい段階に来ていると考えます。
リアルの場で数人で会議する時は、話してほしい人の顔を向いてアイキャッチします。
温まってくるといちいち名前を呼ばなくても、誰が次に話すかキャッチボールがうまく進みます。
ところがオンライン会議は、話している人の口と音声が微妙にずれます。
積極的に話そうとするとかぶってしまうから、発言を控えるようになる。
すると、司会者がいちいち次の発言者を指名しなければなりません。
話を聞いているという印に動作を大きくしないと発言者も反応がわからない。できるだけ、大きくうなずかないと会話がスムースにつながらない。
これが積み重なると意外とストレスになります。
それだけではありません。
ZOOMに代表されるモニター画面にパネル状に顔が並ぶタイプだと、参加者がしゃべるときどこを見ていいのかわからない。
顔ではなく「目線はカメラを見る」は理解しているのです
。でも、どうしてもモニター越しに相手がいると錯覚して動いている顔を見てしまう。
すると発言者は、始終きょろきょろしているので挙動不審に見えてしまいます。
では、モニターに顔が映っていなければ解決するのか。
これも慣れが必要です。
やってみるとわかりますが、何も映っていないモニターを見ながらカメラに向かって話すのはしんどい。
何かの絵が映っていればそれでいいのかと思えば、静止画に向かって話すのも抵抗があります。
こうしたオンライン会議では、いったい何が足りないから話しにくいのか。
それは、頷いてくれたり合槌を打ってくれたりといった動き、臨場感なのです。
やっぱり話し相手が顔出ししていなければ、臨場感を得られにくい。
では、なにか動くものに向かって話せないのでしょうか。
いろいろと考慮した末にちょうど仮想空間サービスFrameVRを見つけました。
仮想空間サービスではアバターに変身して参加します。
アバターを使った会議は、参加者の動きと連動するわけではありませんが、ちょうど良い塩梅に動いたりうなずいたりしてくれます。
アバター同士は近寄ると声が大きくなり、遠ざかると声が小さくなります。
臨場感を演出するという課題の一つの解として、アバターは選択肢となったのです。
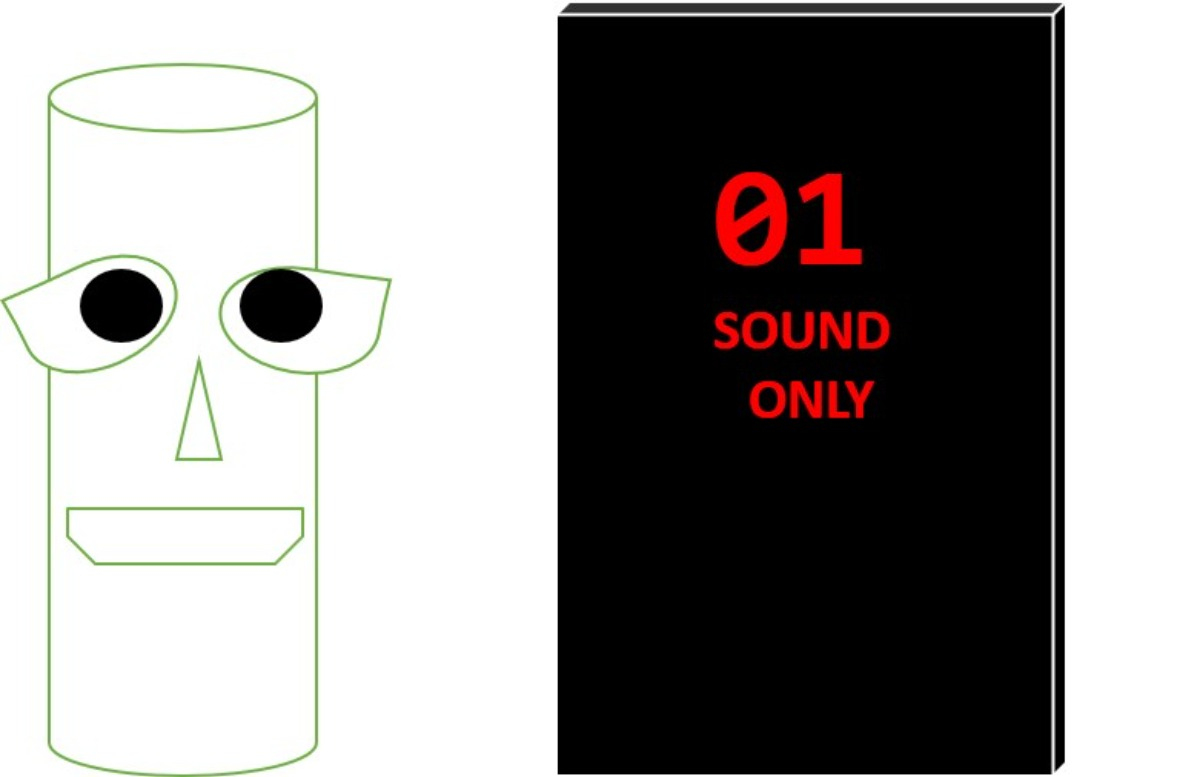
研修に最適なアバターの条件は盛らないシンプルなもの
次の課題は、研修に使うアバターはどれが最適なのか? です。
アバターで研修に参加できるといっても、何でもいいというわけではありません。
研修もビジネスの一環です。
研修の場にふさわしいアバターを選ばなくてはなりません。
テストランでは、本人とよく似たアバターにしたいという要望も寄せられました。
ところが、試行錯誤を繰り返してどんなに似せようとしても、どうしても似たアバターになりません。
いろいろ試して、気が付きました。
本人そっくりにならないのなら、アバターを使うまでもなく、そのまま本人がカメラに映ればよいわけです。
逆に開き直って、どうせアバターを使うなら、むしろ、本人とは似ないほうがいい。
するとこんどは、別の課題が浮上してきました。
本人ソックリになれないのなら、アバターを盛りたいというのです。
「盛る」とは昭和の頃、ゲームセンターに写真を撮ってシールにするプリクラが流行りました。プリクラはデカ目にたり小顔にしたり被写体を加工します。
理想というか、もっとかわいく変身したい。
これが「盛る」です。
お見合い写真も修正しますから「盛る」は文化として定着しているようです。
だから、アバターも盛りたくなる気持ちはわかります。
もちろん、相手から希望を聞いてピッタリのアバターをつくってプレゼンするといったデザイン思考研修なら、それもありです。
もし、いろいろと盛れるアバターをつくれるとなると、ついついそこに集中しがちです。
この盛るは、厄介(やっかい)です。
通勤のとき、現実のファッションは、自分が好きだからと選ぶのならいいのです。
でも、仕事に自信のない人は、自分自身を守り飾るために鎧を身につけます。高いブランド品を身に付ける見栄を張るのも自信を持つための一つです。
好きよりも、周りから見られたい自分をかたちどるファッションを選ぶ。
すると周りから見られたい自分を演じなければなりません。
素の自分ではないのでストレスがたまります。
以前にスポーツ紙の記事で読んだ話です。
野球が大人気の時代、ミスタージャイアンツの背番号3は子供たちの憧れでした。その長嶋茂雄さんは、長嶋茂雄を演じるのは、結構大変なんですよ…」とつぶやいていたというのです。
子供たちのイメージを壊さないように演じ続けていた。これ、一種のアバターです。
長嶋さんほどの天才なら、長嶋茂雄を演じながら実力を発揮できます。
しかし、全員が天才ではありません。
理想の自分を演じながら仕事で、実力を発揮できるでしょうか。
研修でも理想の自分を演じながら、研修課題もこなさなければならない。
疲れそうです。
ビジネス研修で使うには、もっとシンプルなアバターがいいのです。
アバターは研修の小道具です。
あくまでも研修がメイン(主)であり、アバターはサブ(従)です。
できるだけ付加情報を削ぎ落したもアバターが欲しい。
極限までシンプルにしたものが望ましい。せっかくなので先入観も無くしたい。
できるだけ情報を削ると、ワビサビの世界です。
アニメ、エヴァンゲリオンに登場する[SOUND ONLY]という石柱みたいに。
もう、ただの円柱に目が付いているだけのアバターでも構わない。
ここまで考慮した上で、シンプルなアバターを採用しているFrameVRに落ち着きました。
シンプルなアバターなら匿名性に配慮した人材アセスメントが可能
会社のエントランスで掃除をしていたオジサン(またはオバサン)が実は社長だったといった、ストーリーなど昔のドラマでよく見かけたものです。
採用試験に来る人間が、どんな振る舞いをするか。
社長みずから変装して観察していたわけです。
清掃スタッフだからと、ぞんざいな態度をとる受験者は、入社お断りというストーリーが定番です。
ドラマになるくらいですから、それだけ、外見は感覚を惑わすということ。
実際の採用も人材アセスメント(人物及び行動の客観的評価)では、採用試験など一般的なテストだけでは人材を正確に計ることは難しい。
そのため面接などを併用します。
ところが、この面接でもミスマッチが起きやすい。
そこには容姿や見た目というルッキズム(外見にもとづく差別)があります。美女美男であれば、それだけで仕事ができそうに見えてしまう。
古代中国の科挙(かきょ)という官僚採用試験では、容姿も評価対象でしたが、現代では容姿と能力とは切り離すべきです。
けれども、これがなかなか難しい。
もし、シンプルなアバターなら、容姿といった先入観はなくなります。
イベントを通してアバターを観察すれば、純粋に振る舞いを判断できます。
受講者からしても、アバターなら、無理して飾らないで済む。素の状態を安心して晒せます。
なにしろ、本人は特定されないのですから。
むしろ、自己分析ツールを使うまでもなく、受講者自身が知らない自分に気づくこともできるでしょう。
組織の風通しをよくするためにアバターを活用
アバターの副次的な効果として、採用試験のみならず、組織の風通りをよくするミーティングにも使えます。
組織で言いたいことがいえない。
同じ部門ではこれからも一緒に働くわけですから、相手の反応(報復)を気にしていいたいことを我慢する。
仕事は会社は仲良しグループを目指すのではなく、目標を達成しなければなりません。
仲良しグループは、一面から見れば正しいでしょう。
でも、いいたいことがいえない。表面的は仲良しを演じている。我慢して仲良しを演じるが積み重なるとストレスになります。
結果としてストレスから、会社に行きたくない、病欠が増えたり退職に至るケースも多々見てきました。
むしろ職場の愚痴を自由にいえる環境づくりも、風通しが良い組織といえます。
FrameVRを使用した仮想空間サービスは、匿名で意見をいえる聞ける場をつくれます。
アバターとはいえど、注意深く声を聞けば誰の発言なのか特定されてしまうという向きもあるでしょう。そこは、チャットを使うなりボイスチェンジャーアプリを使うなりと柔軟に対処すればいいのです。
これから、新しい新人採用や社内の風通しをよくする研修のこころみとして、FrameVRのアバターを利用した研修を選択肢としてお考えください。
創客営業研究所では、研修担当者様からのさまざまなご要望に応じています。
臨場感ある研修はFrameVRのシンプルなアバターを使うとよい 臨場感 アバター
創客営業研究所
【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます
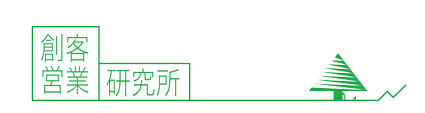
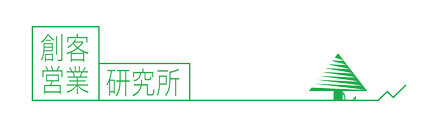
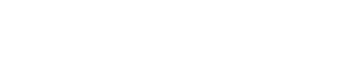







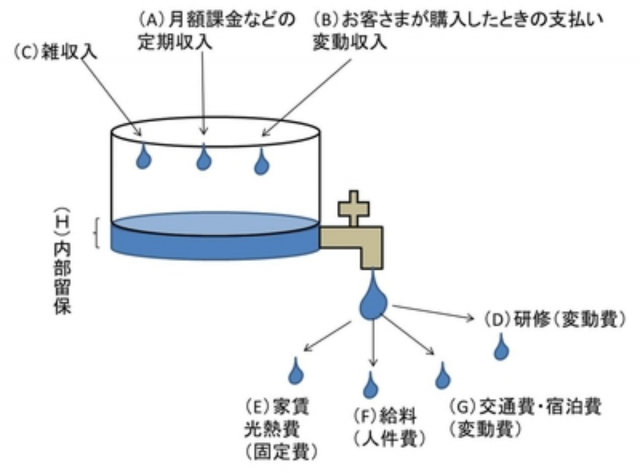

シンプルなアバターを使った研修のまとめ
シンプルなアバターを使った研修は、先入観を排しながらも臨場感があります。
仮想空間では、アバターの容姿に惑わされることなく振る舞いを観察できます。
従来の採用試験を補完でき、職場の不満解消にも役立ちます。