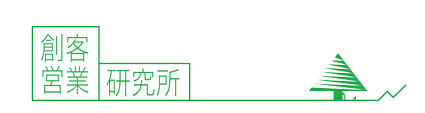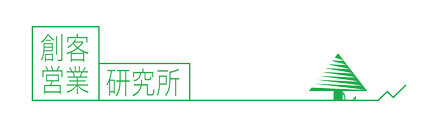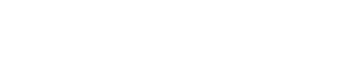タグ一覧
選択したタグ:「課題に気付く」
12件
-
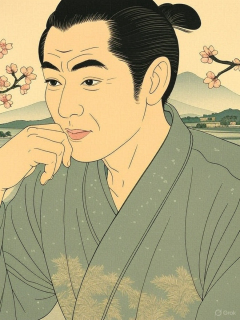
国力の指針としてのGDP信仰の終焉と新しい価値尺度の模索
ラテラルシンキングとは:事例研究
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-6-8
以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/2696bb5d441ccdabae27d2fe3e84e02c AIが木村尚義の読み方を間違っていますが・・・。 本題はここから 国内総生産(GDP)は、ある一定期間内に国内で生産されたすべてのモノやサービスの付加価値の合計額を表す経済指標です。長らくこの数値は、国の経済的な豊かさや国力を測る主要な尺度として、絶対的な信頼を寄せられてきました。しかし、経済活動の成果を一面的な数値で示すGDPだけで、果たして現代社会の複雑な様相や、そこで暮らす人々の真の幸福度まで測りきれるのでしょうか。 GDP信仰は終焉の時に来ているのでは? GDPというレンズを通して見える世界は、もはや社会全体のごく一部しか映し出していないのかもしれません。 かつて日本は、1970年の大阪万博の成功とその後のオイルショックという未曾有の危機を乗り越え、世界から「エコノミックアニマル」とまで評されるほどの企業戦士たちが経済成長を力強く牽引しました。当時の日本企業は、ひたすら利益を追求し、それが国全体の成長エンジンとなっていた時代でした。 しかし、平成に入りバブル経済が崩壊すると、企業は利益一辺倒の姿勢から、社会全体の調和や「世間様の目」をより深く考慮するようになり、その経営姿勢にも変化が求められるようになりました。 こうしたさまざまな視点から、総合的、包括的な、新しい価値尺度を模索しなくてはならない時期に来ています。
-

コミュニケーション下手にはコンテンツ多様化の影
ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-6-4
以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/9ebd407316c90ee74db96360f83d1e27 ここから本題。 ふと、現代社会において、人と人との間のコミュニケーションがどこかぎこちなく、表面的になっているのではないかと感じることがある。雑談が弾まない、相手の考えていることが分からない、あるいはそもそも何を話せばいいのか見当もつかない。こうした「コミュニケーション下手」とも言える状況は、21世紀に入り、特に顕著になってきたように思える。その遠因の一つに、私たちの周りに溢れるコンテンツの爆発的な多様化があるのではないだろうか。 かつて、情報源が限られていた時代には、人々は自然と共通の話題を共有していた。例えば1970年代、家庭にテレビが一台あれば、家族は同じ番組を囲み、翌日には学校や職場でその話題に花を咲かせた。新聞や雑誌も、数少ない情報源として多くの人が目を通し、社会の出来事や流行に対する共通認識が形成されやすかった。
-

新入社員に捧げる成功する社員と残念な社員のたった一つの違い
ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-4-5
新入社員に捧げる成功する社員と残念な社員のたった一つの違いについて。 わたし(木村)は、30年ほど侵入社員の研修をご依頼いただいています。 30年もやっていると、成功する社員と残念な社員の違いもわかってきます。 その前に、ディズニーランドに行ったことありますか? ディズニーランドに限らずテーマパークにいったことありますか? このテーマパークで楽しむコツがあります。 ディズニーランドで楽しむコツは、受け入れること。 「あんなの着ぐるみさ」なんて醒めていると、せっかく入場料を払ったのに、ちっとも楽しくないのです。 楽しむためには、世界観を受け入れることです。 世界的に有名な映画俳優のミッキーに会えた! と思い込めば楽しいわけです。 これ、お約束なのです。 ミッキーが着ぐるみだという人だとしても映画館でスパイダーマンやキャプテンアメリカとか観るでしょう。 そんなときも、「あんなのお話しだ」とか「主人公が勝つに決まっている」なんて観るとやっぱり面白くないと思いませんか? お約束なのです。 それでも、着ぐるみだとかなんだと言っている人は、ヤボと呼ばれるのです。