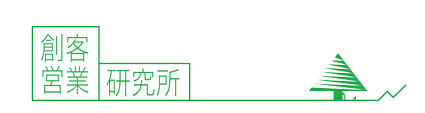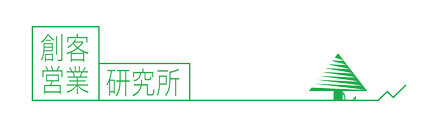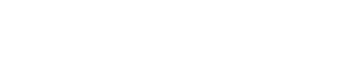タグ一覧
選択したタグ:「教えない授業」
10件
-

AIを利用したディスカッション
ラテラルシンキングとは:新しい考え方
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-12-1
せっかくのAI(今回はGeminiを使っています)なので、3人の性格を作ってお互いディスカッションさせてみました。 プロンプト(召喚呪文?)は以下のとおりです。 1.話させたいテーマ 現在はテスト結果偏重の教育であり、極端にいえばテスト結果で将来が決まってしまう。 長期的に考えるとたかが数年の教育で将来が決まってしまうことは人生のマイナスになるのではないか。そこで非認知能力を伸ばすことに重点を置きたい。 その場合、非認知能力を身につけたかどうかという評価をどのようにするか。結果的にテスト結果偏重と同じ轍を踏まないのか。 2.3人のキャラクターのイメージ キャラA 一人称は「わし」、語尾は「じゃ。」で終わる。老師で学者、科学的論理的に語る。 キャラB 一人称は「ウチ」、語尾は「だっちゃ。」で終わる。感情的で気分屋。 キャラC 一人称は「拙者」、語尾は「ござる。」伝統にこだわる。
-

失敗と自責: 成長を促す心の哲学
ラテラルシンキングとは:新しい考え方
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-10-14
このブログは木村尚義が作成した文章をもとにAI(Gemini、NotebookLM)を利用して作成しています。 AIによる要約 この哲学的な論考は、失敗を成長の糧とするための心の持ちように焦点を当てています。著者は、成功を数えて自信の源とする「ポジティブ」な姿勢と、失敗ばかりに囚われる「ネガティブ」な傾向を対比し、特に失敗への向き合い方の重要性を強調しています。成長の鍵は、自分を過度に責める「自罰」ではなく、自分の行動に起因すると冷静に受け止め改善につなげる「自責」の精神にあると論じています。一方、失敗の原因を外部に押し付ける「他責」は、自己成長の機会を放棄する最も危険な考え方であると警告しており、赤ちゃんが歩くプロセスや一流選手の練習を例に、失敗から反省・修正し再挑戦する重要性を説いています。
-

自由選択は実に面倒だった。敷かれたレールがない21世紀
ラテラルシンキング研修:創造能力開発研修
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-7-15
以下の記事を生成AIによって、ラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/f329477c840a27a810f9d9433cb93b30 日本語の漢字が難しい様子で、読み方をかなり間違っています(笑)。 以下、本題になります。 ---------------------------------------------------------------- 敷かれたレールがなくなってから気付くこと。 高度経済成長期の日本に生を受けた子どもたちに、親や社会が熱心に刷り込んだ成長ストーリーがあった。 それは「一生懸命に勉強して良い学校に入り、そこから良い会社に入社すれば、人生は盤石なものとなり、一生安泰だ」という、ある種の呪文のような物語である。 さらに、この物語には、社内恋愛を経て結婚し、やがて孫の顔を見せてほしいという親世代の切なる願いまで組み込まれていた。 当時の社会の常識は、男性が外で働き、女性は家庭を守るという役割分担が明確だった。 社内結婚であれば、妻は夫の仕事内容や給料水準をあらかじめ把握できており、社宅住まいであれば会社組織の延長線上で近所付き合いも円滑に進む。 まさに、一つの会社が社員の人生、ひいては家族の人生までをも包括的に面倒を見てくれる――場合によっては葬儀に至るまで――という、手厚い保障が存在した。 それはあたかも、一度スタートの列車に乗りさえすれば、終点まで敷かれたレールの上を迷うことなく進み続けられるようなものだった。 江戸時代に遡れば、農家の子は農業を継ぎ、武士の子は領主に仕えるという、さらに強固な「レール」が存在した。 明治維新や関東大震災、第二次世界大戦後の混乱期を経て、社会の形は大きく変わったものの、根底には「先人たちが敷いたレールにさえ乗ってしまえば、一生は安泰である」という共通認識が脈々と流れていたのである。 そこには、未来への漠然とした不安を抱える必要のない、ある種の牧歌的な安心感があった。 この時代は自由選択という考え方は少数派だった。