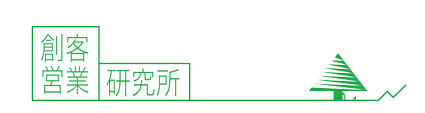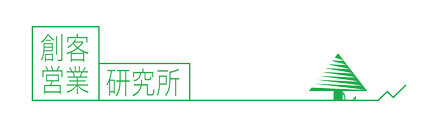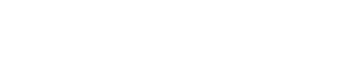タグ一覧
選択したタグ:「ai」
24件
-

AIを利用したディスカッション
ラテラルシンキングとは:新しい考え方
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-12-1
せっかくのAI(今回はGeminiを使っています)なので、3人の性格を作ってお互いディスカッションさせてみました。 プロンプト(召喚呪文?)は以下のとおりです。 1.話させたいテーマ 現在はテスト結果偏重の教育であり、極端にいえばテスト結果で将来が決まってしまう。 長期的に考えるとたかが数年の教育で将来が決まってしまうことは人生のマイナスになるのではないか。そこで非認知能力を伸ばすことに重点を置きたい。 その場合、非認知能力を身につけたかどうかという評価をどのようにするか。結果的にテスト結果偏重と同じ轍を踏まないのか。 2.3人のキャラクターのイメージ キャラA 一人称は「わし」、語尾は「じゃ。」で終わる。老師で学者、科学的論理的に語る。 キャラB 一人称は「ウチ」、語尾は「だっちゃ。」で終わる。感情的で気分屋。 キャラC 一人称は「拙者」、語尾は「ござる。」伝統にこだわる。
-

失敗と自責: 成長を促す心の哲学
ラテラルシンキングとは:新しい考え方
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-10-14
このブログは木村尚義が作成した文章をもとにAI(Gemini、NotebookLM)を利用して作成しています。 AIによる要約 この哲学的な論考は、失敗を成長の糧とするための心の持ちように焦点を当てています。著者は、成功を数えて自信の源とする「ポジティブ」な姿勢と、失敗ばかりに囚われる「ネガティブ」な傾向を対比し、特に失敗への向き合い方の重要性を強調しています。成長の鍵は、自分を過度に責める「自罰」ではなく、自分の行動に起因すると冷静に受け止め改善につなげる「自責」の精神にあると論じています。一方、失敗の原因を外部に押し付ける「他責」は、自己成長の機会を放棄する最も危険な考え方であると警告しており、赤ちゃんが歩くプロセスや一流選手の練習を例に、失敗から反省・修正し再挑戦する重要性を説いています。
-

落ちこぼれこそ求められる能力者
ラテラルシンキングとは:新しい考え方
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-10-1
このブログは木村尚義が作成した文章をもとにAI(Gemini、NotebookLM)を利用して作成しています。 以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/d44ee6bb7fab113fd6c3130e385fa0b8 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 AIによる要約 このテキストは、人工知能(AI)時代において、従来の価値観で「落ちこぼれ」や「不器用」と見なされてきた人々が持つ特殊な能力(落ちこぼれ能力)の重要性を論じています。筆者は、AIが膨大な問題を解決できる超高性能エンジンである一方、「何を問題とするか」という発見は人間に依存すると指摘します。従来の「優秀な」人々は、問題を器用に回避してしまうため、根本的な「不都合の存在」に気づきにくい傾向があるのに対し、「不器用な」人々はその違和感や不便さに敏感であり、AIに与えるべき適切な「問い」(プロンプト)を発掘する役割を担うとしています。したがって、この能力はAIの力を最大限に引き出すための戦略的かつ創造的な「鍵」であり、社会は彼らの「不器用さ」を未来の課題発見能力として再定義する必要があると主張しています。