
生成AIによって、編集者の仕事は変わってくるかも?
生成AIとコラムを書くにあたって相談してみた。
いつもは、自問自答してコラムを書いています。
今回は、グーグルGemini AIを相手に壁打ちしています。
壁打ち:自問自答をテニスの練習のごとく例えていました。
以下はAIに相談した内容。
「コラムを書くので手伝って。テーマは新人研修」
承知いたしました。新人研修のコラムですね。どのような読者を想定されていますか?また、どのような切り口で書くか、何かアイデアはありますか?
例えば、以下のような方向性が考えられます。
新人向け: 新人研修を最大限に活かすための心構えや具体的な準備、研修への臨み方など。
研修担当者向け: 効果的な新人研修の設計や実施のポイント、最近のトレンド、よくある課題とその解決策など。
経営者・人事担当者向け: 新人研修の重要性、投資対効果、組織全体の活性化への貢献など。
社会全体向け: 新人研修のあり方についての問題提起や、これからの時代に求められる新人育成の視点など。
読者層や切り口によって、コラムの構成や内容も大きく変わってきますので、まずはそのあたりを教えていただけますでしょうか?もちろん、まだ具体的なアイデアがなくても大丈夫です。一緒に考えていきましょう。
研修担当者向けに書きたい
研修担当者向けのコラムですね、承知いたしました。
研修担当者の皆様が日々頭を悩ませているであろう、効果的な新人研修の設計・実施について掘り下げていくのはいかがでしょうか?
いくつか切り口をご提案させてください。
「令和の新人」の特性を踏まえた研修設計:
多様な価値観を持つ新人たちに、いかに組織の理念や目標を浸透させるか。
デジタルネイティブ世代への効果的なアプローチとは?
主体性を引き出すための工夫。
研修効果を最大化する最新トレンド:
OJTとOff-JTの効果的な組み合わせ。
オンライン研修の進化と活用法。
内製化と外部委託のメリット・デメリット。
ゲーミフィケーションやアクティブラーニングの導入。
研修担当者が陥りやすい落とし穴と対策:
画一的な研修内容からの脱却。
研修後のフォローアップ体制の構築。
研修効果測定の具体的な方法。
多忙な研修担当者のための効率的な業務術。
新人研修を通して組織を活性化する視点:
新人の早期戦力化と定着。
組織全体の学びの文化醸成。
世代間コミュニケーションの促進。
変化に強い組織を作るための新人育成。
これらの切り口の中で、特に興味のあるものはありますか?もちろん、これらのアイデアを組み合わせたり、全く新しい視点から考えることも可能です。
まずは、どのようなメッセージを研修担当者の皆様に届けたいか、あなたの想いを教えていただけますでしょうか?
画一的な研修から脱却する
変化に強い組織を作るため、即戦力やスペック重視という考え方を脱して、数値にできない曖昧な現象を把握する力を養成する。
なるほど、「変化に強い組織を作るために、即戦力やスペック重視の考え方を脱し、数値にできない曖昧な現象を把握する力を養成する」というテーマですね。非常に興味深く、重要な視点だと思います。
このテーマでコラムを書くとして、以下のような構成案はいかがでしょうか。
タイトル案:
「数値化できない『兆し』を捉える力:変化に強い組織を育む新人研修の新潮流」
「即戦力幻想を超えて:曖昧な情報を読み解き、未来を拓く新人育成へ」
「スペック偏重からの脱却:組織の潜在能力を引き出す『観察力』養成」
構成案:
はじめに:
現代社会を取り巻く変化のスピードと不確実性の高まりに触れ、従来の「即戦力」や「スペック」重視の新人育成の限界を指摘する。
変化に強い組織の必要性を強調し、そのためには数値化できない曖昧な情報を捉える力の重要性を提起する。
なぜ「曖昧な現象を把握する力」が重要なのか:
市場の変化、顧客のニーズの微妙な変化、組織内の潜在的な課題など、数値データだけでは捉えきれない「兆し」の存在を示す具体例を挙げる。
これらの兆しを早期に捉え、対応することの組織にとってのメリット(リスク回避、新たな機会の発見など)を解説する。
「勘」や「経験」といった言葉に潜む、形式知化されていない暗黙知の重要性に触れる。
「曖昧な現象を把握する力」を養成するための新人研修のあり方:
従来の知識習得型研修からの脱却を提唱し、体験型学習やグループワーク、ディスカッションなどを重視する。
具体的な研修内容のアイデア例:
ケーススタディ: 過去の成功事例だけでなく、失敗事例や原因が特定しにくい事例を取り上げ、多角的な視点から分析する。
フィールドワーク: 実際に現場に足を運び、五感を使いながら情報を収集し、表面的なデータだけでは見えない事実を発見する。
ロールプレイング: 顧客や関係者の立場になりきり、言葉の奥にある感情や意図を読み取る練習をする。
アート思考/デザイン思考: 美意識や感性を刺激し、固定観念にとらわれない発想を促す。
内省: 研修を通して感じたこと、考えたことを言語化し、自己認識を深める。
研修担当者が意識すべきポイント:
正解を教えるのではなく、問いを投げかけ、新人が自ら考え、気づきを得るように促すファシリテーション能力。
多様な意見や視点を尊重し、活発な議論を促す場のデザイン。
研修後も学びを継続できるような仕組みづくり(メンター制度、OJTとの連携など)。
「曖昧な現象を把握する力」の評価方法:
数値化が難しい能力であるため、研修中の行動観察、レポートの内容、グループワークでの貢献度、内省の深さなどを多角的に評価する。
自己評価や上司・メンターからのフィードバックを活用する。
長期的な視点で、新人の成長を組織全体でサポートする姿勢の重要性を強調する。
おわりに:
改めて「曖昧な現象を把握する力」が変化に強い組織を作る上で不可欠であることを強調する。
即戦力偏重の考え方から脱却し、未来を見据えた人材育成へのシフトを呼びかける。
研修担当者へのエールで締めくくる。
この構成案について、気になる点やさらに深掘りしたい部分はありますでしょうか?また、読者に特に伝えたいメッセージがあれば教えてください。それらを踏まえて、具体的な内容を一緒に考えていきましょう。
これ、編集者いらないのでは?
わたし、数冊の本を書くにあたって編集者と相談しながら執筆した経験があります。
この生成AI グーグルGeminiとのやり取りは、編集者とほとんど同じです。
おもうに、編集者の仕事も書店に印刷会社や挿絵(これもAIになってくるかも)の意見調整などがメインになっていくのでは?
生成AIは編集者を代行できるようになった 編集者 生成AI
創客営業研究所
【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます
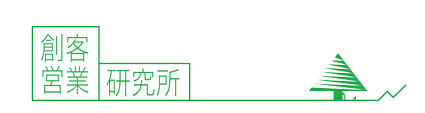
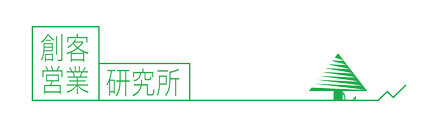
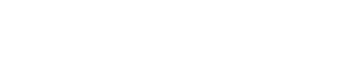







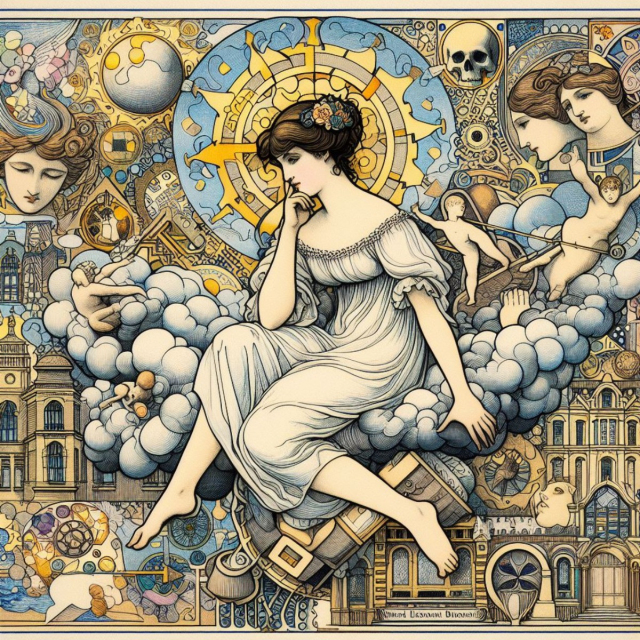



【お問い合わせ】
創客営業研究所の研修を、もっと詳しく知りたいなどのリクエストがありましたら、
「お問い合わせページ」 < https://www.soeiken.net/Inquiries/inquiry > よりご連絡いただければ幸いです。
たくさんの問い合わせがあります。
いち早くお返事をできるように問い合わせ内容の本文に「AIの活用について」とお書き下さるとありがたいです。