
日本を発想大国にする研修会社を目指しています
創客営業研究所では、地方自治体をはじめとしてインフラから金融にITまでと幅広く研修を提供してきました。
日本各地で研修を通して、この「日本を発想大国にする」というテーマを伝えています。
研修で扱っている「ずるい考え方(ラテラルシンキング)」という思考法は古くなりません。
もともと古代バビロニアの時代から千年単位で伝えられてきた古い思考法です。
日本で育った人なら誰でも一休さんや吉四六さんのトンチ話でラテラルシンキングをご存知のはず。
トンチ話は、今までの常識では、対処できないときにどうやって乗り越えたかを物語として伝えてくれるのです。
先の見えないと言われている今日、これからの変革を乗り越えるには、こうした思考法が必要になります。
このコラムでは、ラテラルシンキングのことをもっと知ってもらうため、抽象化について説明します。
名経営者には、歴史小説好きが多い
名経営者とはじめとして仕事上手な人は、歴史小説が好きだと公言している人がたくさんいます。
歴史小説は、時代の変革をテーマにしている話がとても多い。
こうした人は、小説を読むことで、自分がその人物だったらどうするかと考えながら読みます。
壁にぶち当たったら自分ならどう行動するか? というシミュレーションを楽しんでいるのです。
シミレーションを繰り返すことで、自分自身の対処方法の引き出しを増やします。
シミュレーションのバリエーションが増えるに従って応用の範囲が広がります。
仕事上手と呼ばれる人は、歴史のエピソードを自分ごとにして頭の中でシミュレーションを繰り返しています。
こうした思考法を抽象化と呼びます。
本を読んでも上手にいかない人は、もったいない読み方をしているから
ビジネス書のコーナーには、実にさまざまな本が並んでいます。
読者の中には、そんな本をいくら読んでも自分と同じ状況じゃないから使えないという人もいます。
当たり前です。
ビジネスの状況は千差万別です。
まったく同じ状況なんてありえません。
ビジネス書のノウハウなんて、あなたを取り巻く環境によっては、使えたり使えなかったりします。
中小企業では、大企業の社員向けに書かれた本は使えませんし、中小企業の社長向けの本は大企業の役員には使えません。
一口に企業と言っても、ひとくくりにはならず、さまざまな規模があります。
仕事にしても、現場の仕事に管理職にさまざまです。
残念ながらビジネス書を読んでも、まず、合うことはないのです。
さまざまなな事例が紹介されていたとしても、その事例はそのまま使えるわけではありません。
事例は、そのまま使うのではなく、内容をいったん抽象化してから、あなたのビジネスのどの部分に当てはまるかを探します。
時代やタイミング環境が違うから抽象化が必要なのです。
近い抽象化と遠い抽象化
抽象化にも近い抽象化と遠い抽象化があります。
近い抽象化とは、他人のマネ。
誰かが成功するとわかれば、たちまち同じような商売が増えます。
1990年代に折りたたみ式のケータイが登場したら、どの会社も折りたたみ式になります。
2000年代後半にボタンを極力省いたスマホが登場したら、たちまちキーボードのないスマホばかりになりました。
ウーバーイーツが成功事例となれば、たちまち出前館やMenuといった競合が現れます。
成功事例をパクること。
これが、近い抽象化といえます。
パクリは悪いことばかりではありません。
切磋琢磨して、互いに高めていく。
一つの会社がなにかの問題でサービス提供できないときには競合他社が代行することでユーザーに不便を強いないようにする。
こうしたメリットもあるからです。
一方の遠い抽象化は、応用力が必要になります。
歴史書を読んで自分に当てはめるということは、遠い抽象化の例です。
ムリヤリでもあなたの仕事に当てはめるシミュレーションを繰り返すうちに脳の「できる回路」が成長していきます。
抽象化を練習する方法
NHKごっこ。
誰もが知っている物事に別の名前をつけることで、その本質を見つけます。
NHKは、特定の会社の宣伝となるのを避けるため、個別の商品名は違う言葉に言い換えます。
そこで、この手法を使います。
「何をするためのものか」という機能面に注目して、表現を考えます。
名前はモノのイメージを変えます。
例えば、仏教徒は禁止されている酒を飲むために「般若湯(はんにゃとう)」という名前をつけました。「〇〇湯」という薬の名前をつけることで「お酒は薬である」というイメージに替えたわけです。
次の品物を別の名前に変えて下さい。
お題
1.スマートホン
2.シェアハウス
解答例
1.ボタンのない多機能携帯電話
「時間奪い機」と答えた人もいました。
2.文化長屋
いわれてみれば、昔から存在する住居ですね。
このように、良く知られている商品について、固有の名前を使わずに機能で表しましょう。
この練習は商品企画にも使えます。
日本を発想大国にするラテラルシンキングについて ラテラルシンキング 発想大国
創客営業研究所
【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます
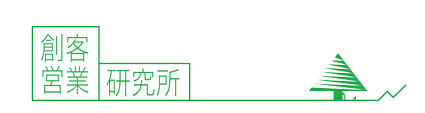
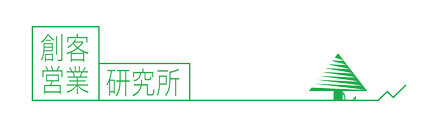
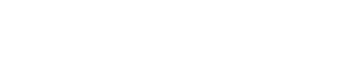







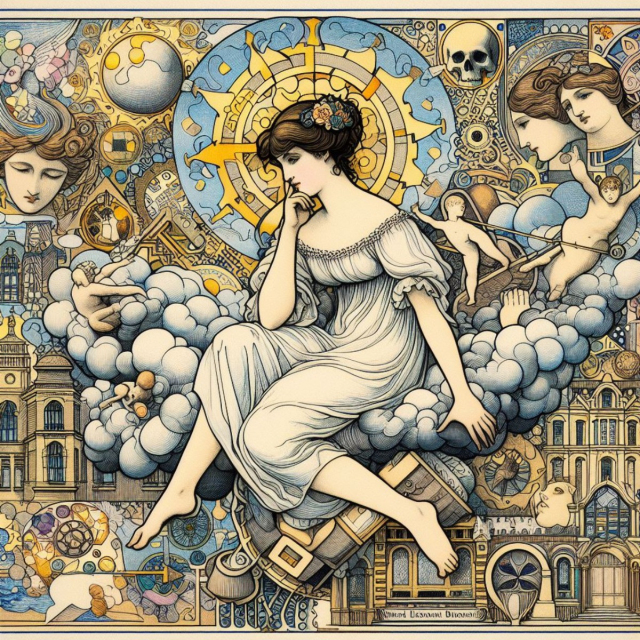



問い合わせ先
■一気読み シリーズ : 木村尚義の「実践! ラテラルシンキング塾」
https://www.business-plus.net/business/columnist/kimuranaoyoshi/series/
■質問などありましたら、どんなに些細なことでも結構です。こちらのURLまでどうぞ。
https://www.soeiken.net/Inquiries/inquiry
たくさんのジャンルから質問をいただいていますので、問い合わせ欄に「ラテラルシンキング研修の相談」とご記入をお願いいたします。
創客営業研究所主催のラテラルシンキング研修は録音・録画が出来ます。