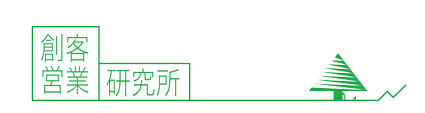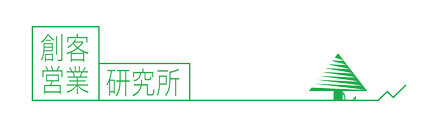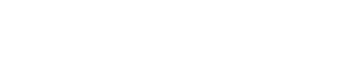タグ一覧
選択したタグ:「ai」
24件
-

俺はお前より偉いというマウントの歴史に終止符を打つ
ラテラルシンキング研修:創造能力開発研修
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-6-24
以下の記事を生成AIによってラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/7d7e26086a8756392fb73c29dfe12d47 本題はこちらから。 ------------------------------------------------------- 私たちの日常に、まるで空気のように蔓延している「マウンティング」という行為。 SNSを開けば誰かが自身の成功や幸福を誇示し、職場ではさりげない会話の中に序列を確認し合うような棘が潜む。 この「俺はお前より偉い」と無言の圧力をかける行為の起源は、驚くべきことにサルの社会にあるという。 サル山のボス猿が、実際の闘争による怪我を避けるため、ギーギーと威嚇の声を張り上げて己の優位性を示す儀式。それがマウントの原型だ。 人間社会もまた、姿形を変えながら、この原始的な儀式を延々と繰り返してきた。物理的な怪我を避ける知恵は働かせても、精神的な消耗戦からは一向に抜け出せない。一体なぜ、私たちはこれほどまでに他者との比較に囚われ、優位に立つことを渇望するのだろうか。その答えを探るには、人類が繰り広げてきた壮大で、そして少しばかり滑稽なマウントの歴史を紐解く必要がある。
-
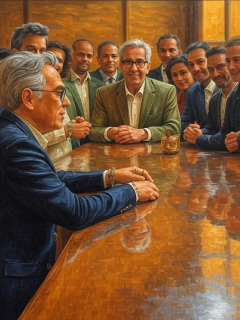
成功の証とはなにか?
ラテラルシンキング研修:創造能力開発研修
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-6-16
以下の記事を生成AIによって、ラジオDJ風、音声コンテンツ(mp3形式)にしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/fd33a259d444db13c4d8f726ba323f3b 本題はここから --------------------------------------- かつて、私たちの社会には、誰もが一目で理解できる「成功の証」が厳然として存在した。 それは多くの場合、「富」という形をとり、高価な腕時計や高級車、そして誰もが知るブランド品で全身を固めることによって、その達成は周囲に示された。人間の外見に、生物学的な優劣がさほど存在しないからこそ、人々は後天的に獲得した富を可視化することで、自らの成功を他者に認めさせようとしたのかもしれない。 その輝きは、多くの人々の羨望を集め、また新たな成功を目指す者たちの道標となっていた。しかし、時代の潮流が大きく変わった今、その絶対的とも思えた成功の物差しは、その輝きを失いつつある。多様な価値観が芽吹き、受け入れられるようになった現代において、唯一無二の「成功の証」は、もはやどこにも見当たらない。 この大きな価値観の転換点には、一九八〇年代後半から九〇年代初頭にかけて日本社会を席巻した、いわゆるバブル経済とその崩壊の経験がある。土地や株価が異常な高騰を見せたあの時代、富はまるで天から降ってくるかのように一部の人々のもとに集まった。 そして、その富を誇示するかのように、きらびやかな消費文化が花開いた。しかし、その熱狂が過ぎ去った後、私たちに残されたのは、お金が必ずしも幸福の絶対的な保証にはならないという、ある種の虚無感を伴ったリアリズムであった。 週刊誌やワイドショーといったゴシップメディアは、バブルの寵児ともてはやされた成功者たちのその後の転落を、好んで報じるようになった。 派手な暮らしの裏にあった家庭の不和、財産をめぐる骨肉の争いの果ての殺人事件、あるいは事業の失敗を苦にした自殺。そうしたニュースは、大衆の心に静かに浸透していった。 もちろん、その中には、他者の不幸を蜜の味とする「シャーデンフロイデ」を刺激するために、面白おかしく、あるいは誇張されて伝えられたフェイクもあっただろう。だが、たとえそうだとしても、「富裕層=幸福」という単純な図式が、もはや成り立たないことは、誰の目にも明らかとなったのである。
-
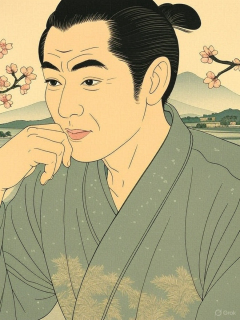
国力の指針としてのGDP信仰の終焉と新しい価値尺度の模索
ラテラルシンキングとは:事例研究
創客営業研究所
創客営業研究所の記事
東京都中央区銀座6-6-1
2025-6-8
以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/2696bb5d441ccdabae27d2fe3e84e02c AIが木村尚義の読み方を間違っていますが・・・。 本題はここから 国内総生産(GDP)は、ある一定期間内に国内で生産されたすべてのモノやサービスの付加価値の合計額を表す経済指標です。長らくこの数値は、国の経済的な豊かさや国力を測る主要な尺度として、絶対的な信頼を寄せられてきました。しかし、経済活動の成果を一面的な数値で示すGDPだけで、果たして現代社会の複雑な様相や、そこで暮らす人々の真の幸福度まで測りきれるのでしょうか。 GDP信仰は終焉の時に来ているのでは? GDPというレンズを通して見える世界は、もはや社会全体のごく一部しか映し出していないのかもしれません。 かつて日本は、1970年の大阪万博の成功とその後のオイルショックという未曾有の危機を乗り越え、世界から「エコノミックアニマル」とまで評されるほどの企業戦士たちが経済成長を力強く牽引しました。当時の日本企業は、ひたすら利益を追求し、それが国全体の成長エンジンとなっていた時代でした。 しかし、平成に入りバブル経済が崩壊すると、企業は利益一辺倒の姿勢から、社会全体の調和や「世間様の目」をより深く考慮するようになり、その経営姿勢にも変化が求められるようになりました。 こうしたさまざまな視点から、総合的、包括的な、新しい価値尺度を模索しなくてはならない時期に来ています。