教えられて100点満点を目指す方式は限界にきた。自分で考えるにはラテラルシンキング
ラテラルシンキング社員研修:事業革新研修
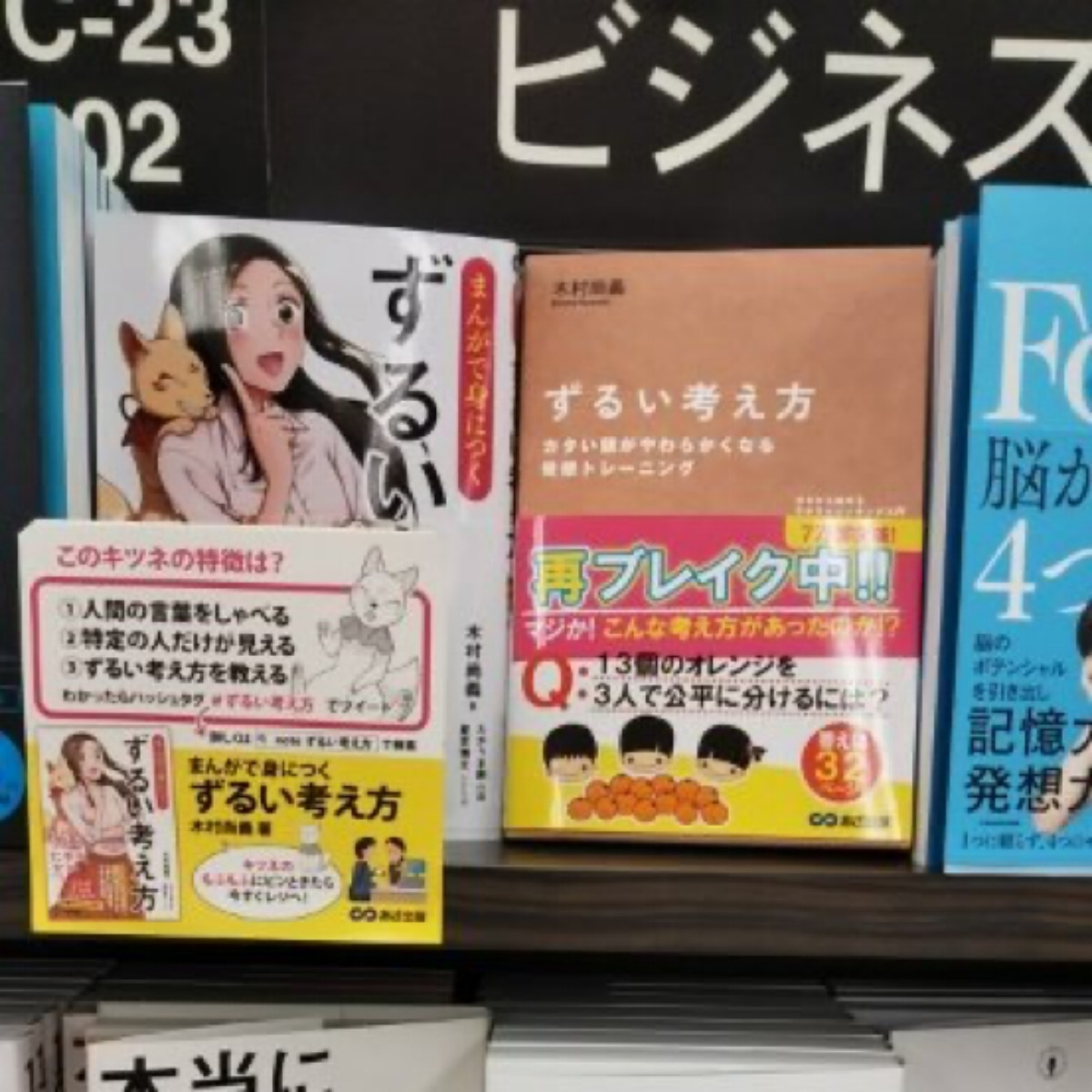
100点満点を目指す方式は限界で、もう今までの方法論では教えられなくなった
今も昔も学校教育では減点方式の競争原理を徹底的に叩き込まれます。
なんの話かというと、ここ数十年の間、学校のテストでは100点満点を目指す方式は、まったく変わっていないということです。
選択を間違えれば減点される。
つまり、学校教育は昔からずっと減点主義なわけです。
最終的に卒業するまで、減点が少なければ優秀ということになります。
そして、この100点満点の設問と選択肢は、誰が決めるのかといえば、あらかじめ先生によって設定されています。
当然ですね。
ということは、学校教育では、出題する先生の傾向を考慮して100点満点になるような対策をしさえすれば「優秀」ということになるわけです。
この優秀な学生を輩出する教育方針は、少なくとも1970年代-1980年代までは、とても良く機能していました。
いわゆる3C、カラーテレビ、クーラー、カー(自家用車)がよく売れた時代です。
高度成長により豊かになった時代(とりわけ顕著なのは1960年代です。70年代にはオイルショック、ドルショックに立て続けに見舞われ公害問題も顕著になります)なので、お金があるけれどモノの生産が間に合わないから買えない。
モノさえあれば、多少高くても買う。品質なんかよりも入手できることが重要でした。
消費者の側も今のように「価格を比較して、できるだけ安く買う」のではなく「手に入るのであれば高くても買う」という状況でした。
ところが、価値観が変わり、今までの正解が何かわからなくなりました。
正解がわからないから100点満点だとしても、それは間違った正解なのです。
たとえば、昭和の運動部は汗をかくと疲れるから水を飲むなと教えられました。これが正解だったのです。
令和の正解は、脱水症状を起こす前に十分水分を取るようにと正解が変わっているのです。
だから、現代では正解がわからない。それでいて過去問で100点をとって満足してる。
それが100点満点を目指す方式は限界ということです。成功法則がわからないので、もう教えられなくなったのです。
教えられなければ、自分で考えるしかありません。
明治から昭和までは、全員が同じ考え方をすると都合がよかった時代
昭和までの時代は、作りさえすれば買ってくれた時代です。
少し前の中国人観光客が日本で爆買したように、モノさえあればあるだけ買って帰ったのです。
こうした爆買はありがたいもので、会社としても売り先さえ決まっているのなら、いくら投資しても無駄になりません。
正解がわかっていた時代です。
当選番号のわかっている宝くじを買うようなものだからです。
日本の高度成長期に話を戻すと、当時の欧米各国の流行は、フラフープやフリスビーのように時間差で日本でも流行します。そのためには、いかに早く欧米の流行をキャッチアップすることが大切だと言われていました。(今でも電動スクーターやハンドスピナーなど欧米で流行って日本に上陸しているものもあります)
そんな時代ですから他社より早く欧米情報を入手して、社員全員が量産に向けて同様に行動することが求められます。
製品改良のアイデアなど不要です。
製品を改良しようとして、万が一の製造ミスにより生産が滞るよりは、多少の不具合を知っていたとしても、それには目をつぶり、すでに売れるという「正解」がわかっている現行品を大量に用意することを最優先していました。
さらには昭和の最後から平成初期のバブルの時代になれば溢れたお金で土地を買って値上がりしたら売ってを繰り返して、ものがさらにたくさん売れました。
そんな時代背景では、社員全員が同じ行動をとった方が効率が良い。つまり、社員全員に会社が決めたの行動をとることに100点満点を求めたます。
こうした社会(業界)の要望に従って「上から落ちてきたことをよく守る」ような教育を提供しているのです。現在でもその延長で先生が考えた選択肢から選ぶ、マークシート方式のテストが主流のままです。
前提を教えられなくなった古株社員と教えて貰おうとする現役社員
とはいえ、1970年代から続いた経済成長にも陰りが見えてきます。
終戦直後に、ずっと下位にあった日本の経済成長ランキングが上から数えたほうが早くなると、欧米各国が陥っている先進国病にかかります。
つまり、欧米というお手本が使えなくなったのです。追い打ちをかけるように1991年にバブルが崩壊した途端に「土地さえ持っておけばいずれ高く売れる」という正解すらもなくなってしまいました。
決して倒産しないハズの拓殖銀行に長銀、山一證券の破綻を目の当たりしにして正解がわからなくなります。
2010年以降は、かつては世界を席巻したウォークマンのソニー、ユニークな目のつけどころのシャープ、堅実な経営と思われていたはずの東芝までも、苦境に陥っています。かつての正解は今となっては不正解なのです。もう、正解は誰にもわからない。
ところが学校教育では、選択肢から正解を素早く選ぶという教育効果測定の方法は旧態依然として残っています。
その結果、新規入社した優秀な学生といえど、上から落ちてきたことを正確に守ったからといっても成果が上げられないわけです。
成果が上がらないから古株社員に相談します。実は、その古株社員も成果が上がらず悩んでいるのですが、一生懸命働けば、いずれ成果が出るとというアドバイスしかできません。
そんなアドバイスしか出来ない社員だとしても、一概に悪いとはいえないのです。
多少の落ち込みはあったとしても「一生懸命働けば成果が出る」という、正解があった時代を何十年も体験してきたからです。
正解がないときには、自分で課題と答えを見つけるしかない
大半の会社員は正解がなくなったことに、とっくに気が付いてけれども、会社に勤め続けているというところが現実でしょう。
古株社員も、そのまた昔の時代に活躍していた社員から一生懸命やれと言われても、もはや、一生懸命に働いたとしても成果が出るかどうかわからない。
それでも、会社は回さなければなりません。
過去と同じことをやるのが一番ラクです。
おかしいと思っていても、過去の再現をしようとします。
新入社員が入ってきたら、一生懸命働けば成果が出るという前提は、自分自身で納得していないとしても、そうしたものだと教えなければなりません。
こうして、現状とズレた教えが繰り返されて、現在に至っています。
そろそろ、前提が違ってきたから、会社も手探りで仕事をしているのだと認めなければいけない時期に来ているのです。
北原白秋の「まちぼうけ」という童謡を思い出します。
ある日、畑を耕していたら、木の切り株にぶつかってウサギが取れた。これに味をしめて、クワを捨てて毎日ウサギを待っていたが二度と来なかった。
「守株」ということわざです。
過去にうまく行ったので、同じことをやれば同じ様に成果が出るはず。
正解がないときには、自分で課題を見つけ答えを見つけるしかありません。
まずは、課題に気付く考え方が必要になります。
歴史的の変革期には課題に気付く考え方が重要
歴史的に概念、価値観など信じるものが変わる時期がありました。
時代の変革期です。
平安時代は、短歌が作れることが出世の条件でした。
戦国時代には、価値観が変わり、腕っぷしが強いことが出世の条件です。
昭和の頃は、優秀な子供に対して「末は、博士か大臣か」と期待されました。
昭和の終わりから平成にバブルが全盛になり、偉い人の条件がお金持ちに変わったのです。
そして、令和になって次に何を信じていいのかわからない状況です。
こうした時代には、すこし変わった人が現れます。
トンチ話で有名な一休さんにしても、鎌倉から室町時代になり、戦乱の世の中に一区切りついて価値観が変わったころに活躍しています。
変わった人というのは、既成概念と違う考え方ができる人なのです。
当然のことながら、みなが普通と思っている「常識」を信じていないので変わった行動をする、変わった人ということになります。
常識を信じていると、間違った行動でも正しいと思ってしまいます。
間違っていることに気が付くことは、課題に気が付くということでもあるのです。
将来的にはこういった価値観が変わる、だから、ここがきっと課題になるだろうという気付きです。
かんたんにできる練習を一つ紹介します。
困った事態に出会ったときに一言。
「だが、それがいい」
「だが、それがいい」というフレーズは、ダメだと思っている事実を受け入れて、意味づけを変えます。
これは、マンガ『花の慶次』のセリフなので、ご存じの方も多いでしょう。
このセリフは視点を変えるきっかけに使うと効果的です。
困った状況を目の前にして、「だが、それがいい」と言ったとたんに、
脳は勝手に、“なぜ、いいのか”という理由を探して辻褄を合わせようとします。
この過程で、脳に新たな発想回路が生まれ課題に気付くことができるのです。
こうした練習方法を知っておけば、課題に気付きます。
課題にさえ気付けば、答えはいくらでもでてきます。
まずは、解決する前に課題の存在に気付くことです。
教えられない時代の対策に自分で課題を考えるラテラルシンキング 自分で考える 教えられなくなった
創客営業研究所
【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます
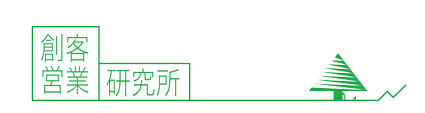
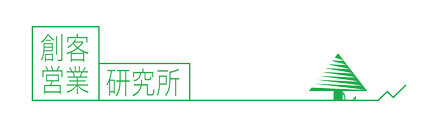
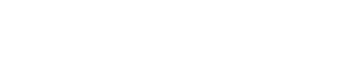

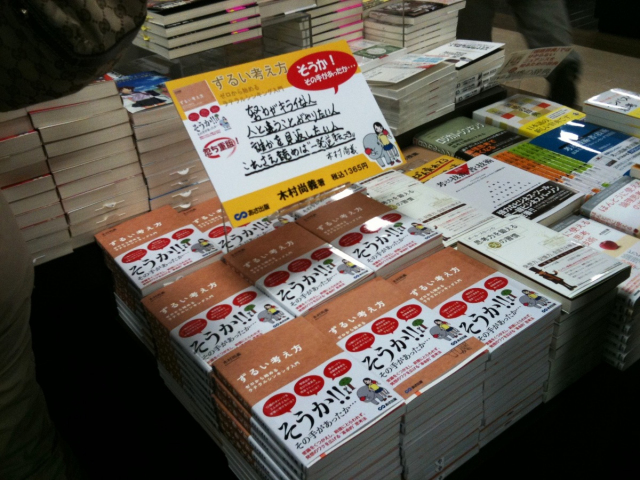

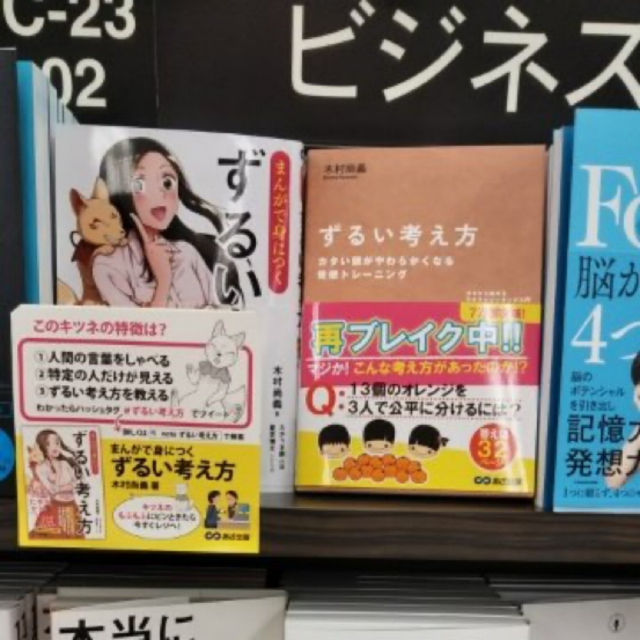
問い合わせ先
■一気読み シリーズ : 木村尚義の「実践! ラテラルシンキング塾」
https://www.business-plus.net/business/columnist/kimuranaoyoshi/series/
■質問などありましたら、どんなに些細なことでも結構です。こちらのURLまでどうぞ。
https://www.soeiken.net/Inquiries/inquiry
たくさんのジャンルから質問をいただいていますので、問い合わせ欄に「ラテラルシンキング研修の相談」とご記入をお願いいたします。
創客営業研究所主催のラテラルシンキング研修は録音・録画が出来ます。